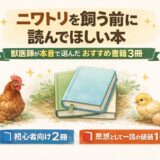はじめに:身近に感じる鳥インフルエンザ
先日、北海道で飼養羽数45万羽の養鶏場から高病原性鳥インフルエンザの発生され殺処分が行われた報告がされました。
ニュースでは大規模農場が取り上げられがちですが、実は数羽しか飼っていない家庭飼育や小規模飼養でも発生リスクはあります。
私自身、数羽の鶏を飼育しており、「うちは少ないから大丈夫」と思っていた時期もありました。
しかし、山口県で23羽しか飼育していないにも拘わらず鳥インフルエンザが確認されたという事例を知り改めて考えさせられました。
もう一つ「使用衛生管理基準を守っていない場合の手当金減額が厳正化される」という制度改正です。
少数飼育の場合は金額の大小はそれほどの問題ではありませんが、山口県の事例では義務である定期報告の提出や飼養衛生管理基準が守られていなかったことが問題視されていました。
また、発生すると10km圏内に存在する鶏の搬出(出荷など)が制限されます。
社会への影響が大きいため大規模・小規模に関わらず鶏の飼育者一丸となって鳥インフルエンザの対策を進めていく必要があるようです。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/kouhukin.html
手当金減額の新ルールとは?
これまで、鳥インフルエンザが発生して鶏が殺処分された場合、原則として国から手当金(補償金)が支払われてきました。
しかし、今後は**「飼養衛生管理基準」に基づく管理を適切に行っていなかった場合、手当金が減額される**ようになります。
つまり、
- 消毒の不備:長靴の交換、手袋の交換、飲水消毒を行っていない。
- 野生鳥獣対策の不備:防鳥ネットが破れて放置されていたなど
- 記録の不備:入退場者の記録や定期報告などを行っていない。
- 早期通報違反:疑わしい異常があったにもかかわらず家畜保健衛生所に通報を行わなかった。
といった状態だと、
「管理不足」とみなされ、補償の対象が一部減額される可能性があるのです。
これらの減額率の上限はありません。(現在のところ最大でも33%の減額にとどまっています)
この基準は、大規模養鶏場だけでなく、少数飼育者も対象になります。
「たった数羽だから」と油断してはいけない――ということですね。
山口県の少数飼育での発生事例
2024年1月、山口県内で23羽規模の少数飼育鶏が高病原性鳥インフルエンザに感染した事例がありました。
発見のきっかけは、飼い主が4日で9羽が立て続けに死亡し保健所に通報したこと。
検査の結果、感染が確認され、半径数キロ圏内の防疫区域が設定されました。
国や県の検証の結果、野鳥が感染源である可能性が高いとされています。
行政も迅速に対応し、1,2日で殺処分や緊急消毒を終了し飛び火もなく終息しました。
近所にため池や農業用水があり、渡り鳥が確認されており、ハイリスクな環境である一方で野鳥対策が十分にされていなかったとの報告がなされています。
また、定期報告がされておらず、家畜保健衛生所の指導を受けていなかったことが指摘されていました。
「義務の履行、衛生管理の徹底がいかに重要か」が改めて浮き彫りになりました。
少数飼育者ができる「飼養衛生管理基準」の実践ポイント
正直に言えば、家庭規模の飼育で、すべての衛生管理を完璧に行うのは大変です。
でも、「できる範囲で継続する」ことが何より大切です。
ここでは、特に少数飼育者でも実践しやすいポイントを紹介します👇
🔸防鳥ネットの点検
- 穴や破れがないか定期的にチェック
- 野鳥と接触がないようにする。
- 特に野鳥が多い時期(秋〜冬)は放牧などは行わない。
🔸出入口の消毒
- 鶏舎の前に消毒マットを設置
- 長靴や器具を使い回さず定期的に消毒する
🔸給餌・給水の衛生
- 野鳥が飲めないように工夫
- 飼料・水は屋内に保管
- 水道水以外を使用するときは消毒を行う。
これらを実践するだけでも、感染リスクは大きく下げられます。
また、いざというとき「衛生管理をしていた」と言える、
手当金の減額を防ぐための“証拠”にもなり、自分の身を守ることにつながります。
まとめ:自分の鶏と地域を守るために
今回の制度改正は、単なる罰則ではなく、
**「飼い主自身を守るためのルール」**です。
少数飼育でも、衛生管理の意識を持つことは地域全体のリスクを減らすことにつながります。
発生を完全に防ぐことが難しいことは国、家畜保健衛生所、養鶏業に携わる人の全員がわかっています。
それでも一度発生すると関係機関や地域に大きな影響を与えてしまいます。
鳥インフルエンザに対し地域一丸となって立ち向かえるよう我々も協力していかないといけないと思いました。
私も、今一度自分の鶏舎を点検し、できる範囲の管理を見直しました。
「守るための基準」――
そう考えることで、日々の小さな積み重ねも前向きに続けていけるのではないでしょうか。
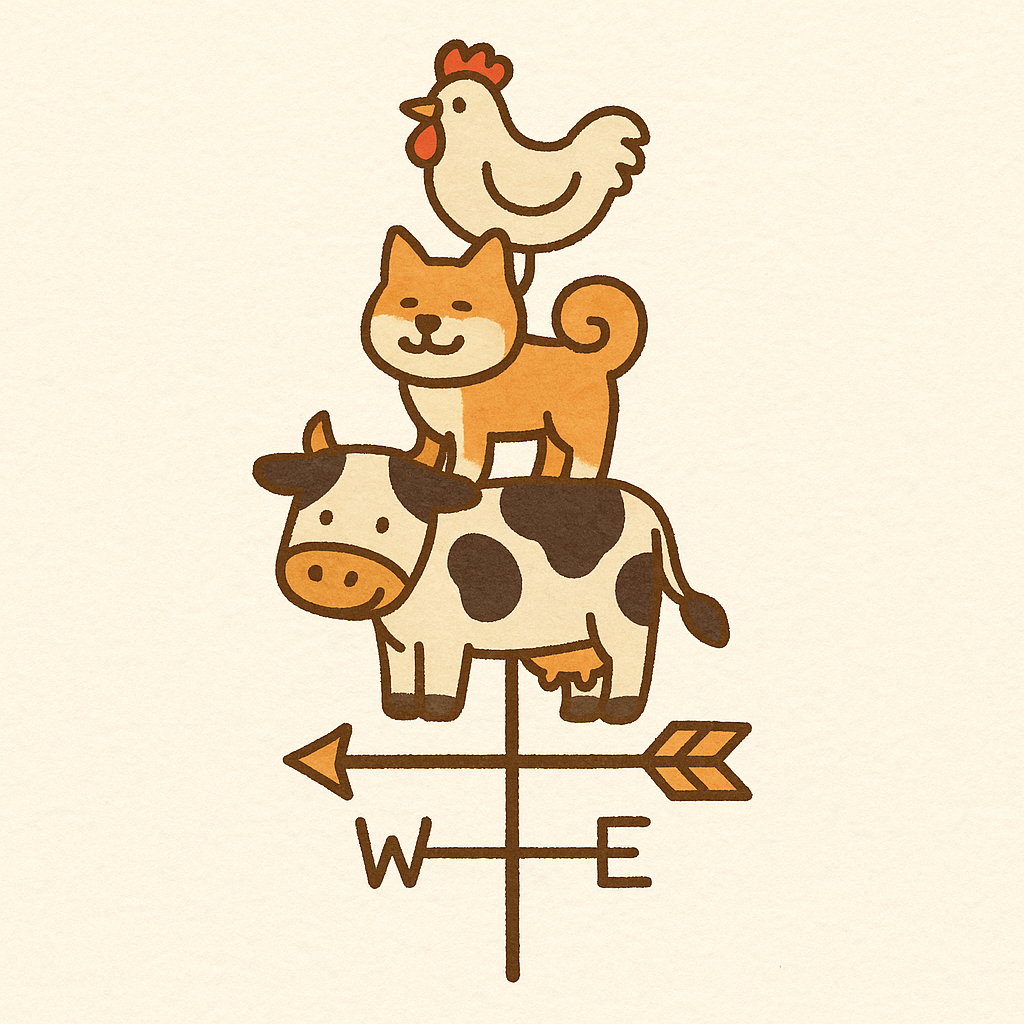 庭には2羽ニワトリがいる
庭には2羽ニワトリがいる